はじめに
「キャッチャーってなんでホームランが少ないの?」
野球ファンなら、一度は浮かんだことがある素朴な疑問。でもこれ、実は奥が深いんです。
この記事では、キャッチャーというポジションに特有の“打てなさ”の理由を、多角的にひも解いていきます。単なる体力や技術の問題ではなく、起用方針や野球界の構造までもが関係しているんです。
1. 守備という名の“消耗戦”
キャッチャーの試合中の仕事量、想像以上です。
投手のリード、配球、サイン、守備位置の指示──さらに盗塁を防ぎ、全投球を正確に受け止める。ほとんど“捕球業務の司令塔”。
この集中力の連続は、打席での爆発力を削いでしまう。
打撃へのリソースが物理的にも精神的にも不足しがちなのです。
2. 「打てなくてもいい」が起用方針に潜む罠
球団がキャッチャーに求めるのは、まず守備力、次いで投手との連携、最後に打撃。
「打てるキャッチャー」より「守れるキャッチャー」のほうが重宝される。
たとえば巨人・大城卓三選手。打撃型でありながら、守備面の評価が低迷すると即座に二軍行きという現実も。
この現象、捕手だけに起こる“評価の逆転現象”とも言えるでしょう。
3. 打撃練習の「迷信」とプロの反論
「キャッチャーは練習時間が足りないから打てない」。
よく言われるこの説ですが、元ロッテの名捕手・里崎智也氏はこれを一蹴。
「他の野手と同じだけ打撃練習してる。打てないのは言い訳だ」と断言しています。
つまり、練習量よりも“打撃へ全力投球できない構造”が問題ということです。
4. 身体的なリスクと“フルスイング”の相性
試合中ずっとしゃがみ続け、クロスプレーで体当たりもある──そんな肉体的酷使が前提の捕手は、スイングのキレを保ちづらいのが現実。
腰・膝・肩への負担は打者としての“芯”を崩すこともしばしば。
5. 育成の段階から「打てる捕手」はレア
アマチュア時代から「守れる捕手」が優遇され、打撃特化型は他ポジションへ回されがち。
結果として、プロに上がってくるキャッチャーの大半が「打てない前提」で育成されているのです。
6. 追い討ちをかける「飛ばないボール」と投高打低
2024年シーズン、NPB全体でホームランが激減。
要因は「飛ばないボール」こと低反発球の採用や、投手力のインフレ。
当然、元々ホームランが出にくい捕手が、最初に割を食います。
| 年度 | 捕手の平均HR数 | 全体HR数(参考) | 主因 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.2本 | 中間的水準 | 通常反発球 |
| 2024 | 2.7本(想定) | 減少傾向 | 低反発球+投手優位 |
(※一部推計値を含む)
まとめ
- 守備負担と起用方針により、打撃への期待がそもそも低い。
- 打撃練習時間の神話は否定されているが、身体的ハンディは無視できない。
- アマからプロへの構造、そして現在の投高打低環境──すべてが打撃力を削いでいる。
キャッチャーとは、“守ることにすべてを捧げる宿命のポジション”。
その代償として、ホームランはいつだって遠い。
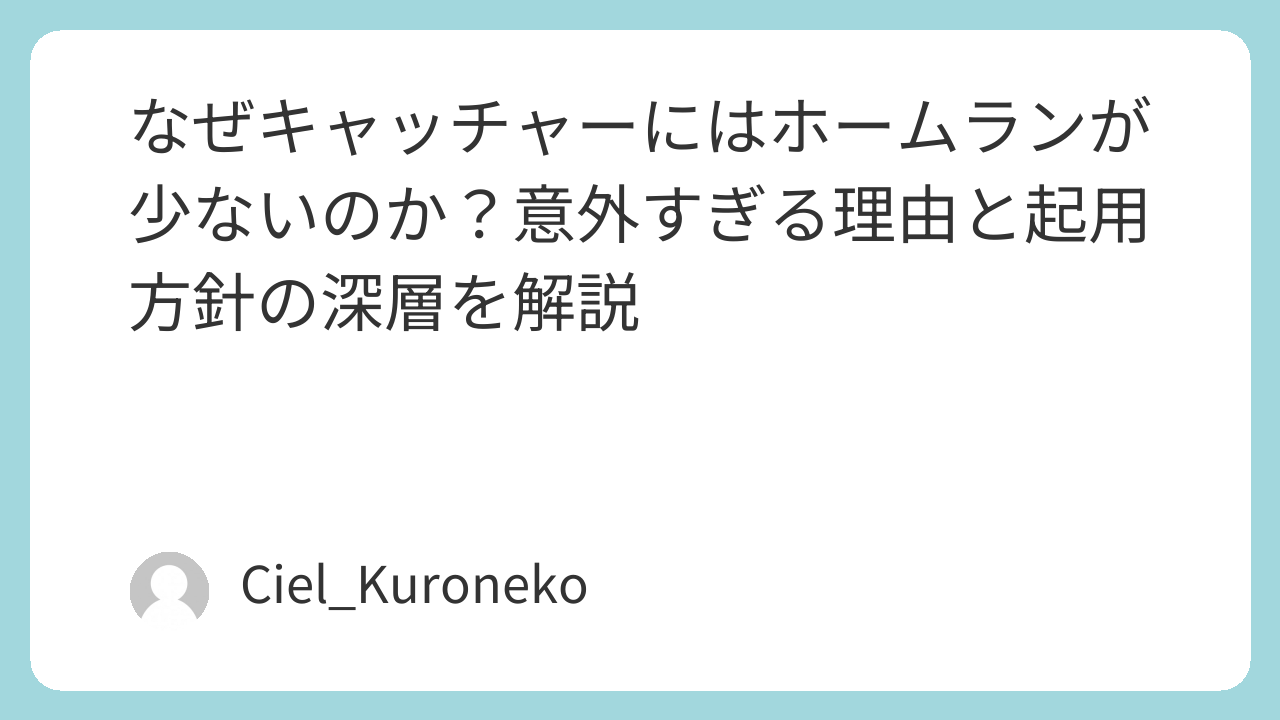
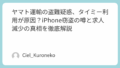
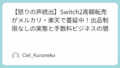
コメント